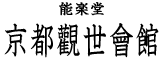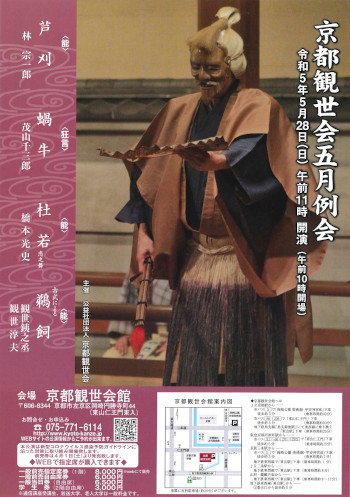京都観世会5月例会
Monthly Performances (May)
公演日時:2023/05/28(日・SUN) 11:00~
主催:京都観世会
主催:京都観世会
演目:
(能) 芦 刈 林 宗一郎
(狂言)蝸 牛 茂山千三郎
(能) 杜 若 恋之舞 橋本 光史
(能) 芦 刈 林 宗一郎
(狂言)蝸 牛 茂山千三郎
(能) 杜 若 恋之舞 橋本 光史
古式による
(能) 鵜 飼 観世銕之丞
観世 淳夫
入場料:
一般前売指定席券※WEB ¥8,000
一般前売自由席券 ¥6,000
一般当日券 (自由席) ¥6,500
学生券 (2階自由席のみ) ¥3,000
特別会員年間会費(会員券10枚) ¥75,000
普通会員年間会費(会員券10枚) ¥43,000
6回会員年間会費(会員券6枚) ¥30,000
一般前売指定席券※WEB ¥8,000
一般前売自由席券 ¥6,000
一般当日券 (自由席) ¥6,500
学生券 (2階自由席のみ) ¥3,000
※通信講座受講生、放送大学、老人大学は一般料金です。
WEB予約・購入はこちら・・・・・・・・・例会会員入場券の年間会費・・・・・・・・・・
普通会員様と6回会員様は、会員券1枚につき2,000円の追加料金で
WEBにて事前指定が可能です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特別会員年間会費(会員券10枚) ¥75,000
普通会員年間会費(会員券10枚) ¥43,000
6回会員年間会費(会員券6枚) ¥30,000
演目解説
そこへ笠をかぶり、刈った蘆をかたげた蘆売りの男が来る。左衛門は刈った蘆を、ハヤリ歌などを取り入れた売り声も風流に、「おあし(・・)添へて召されよ」などと、おもしろおかしく売っている。春の浦の風光を愛で、笠づくしの舞を舞う。じつは零落した左衛門の世を渡る姿であった。そして買ってもらった蘆を渡すときに、思いがけず妻の姿を見、身を恥じて近くの小屋へ身を隠す。妻はその小屋へ近づき、左衛門に「いかにいにしへ人。わらはこそこれまで参りて候へ」と声をかけ、互いに歌を詠み交わして心もうちとけ再会する。烏帽子、直垂を着した左衛門は、和歌の徳を語り、すすめられるままに舞を舞い、夫婦うち連れて都に上るのだった。
やがて色鮮やかな唐衣、透額の冠を着け僧の前に現れ、これこそ歌に詠まれた唐衣、高子の后の御衣。冠は業平が豊の明りの五節の舞のときの形見のものなので身に添え持っていると言い、実は自分は杜若の精で「植え置きし昔の宿の杜若色ばかりこそ昔なりけれ」という歌も、女が杜若になった昔語だという。また業平は歌舞の菩薩の生まれ変わりで、その和歌の言葉が経文となり草木までも成仏すると教え『伊勢物語』の巻々の業平の恋物語りを舞い、夜が白むとともに杜若の精も悟りの心を開き消えていく。
古式による
鵜 飼
旅の僧が甲斐国石和で宿を求めるが、貸してもらえず、川沿いの御堂に泊まる。そこに鵜使いの老人がやってくる。僧は鵜使いの老人に殺生戒を説く。従僧は、昔この辺を通った時にこのような鵜使いに殺生戒を諭し、一夜の宿の接待を受けたことを思い出し、話す。老人はその鵜使いが死んだことを物語る。―昔、石和には禁漁区があった。しかしその鵜使いは夜な夜な忍んで鵜を使って漁をしたところ、見つかり、ふしづけ(す巻き)にされた、という。―老人は語り終わると、実は自分はその鵜使いの幽霊であると明かす。僧は罪障懺悔に鵜を使うよう所望する。老人は鵜を使って見せるが、やがて闇に消える。 〈中入〉僧が法華経で弔うと閻魔の下官(倶生神)が現れ、無間地獄に堕とすべき鵜使いを、僧の回向と、かつての一僧一宿の功力によって、仏所へ送りかえるのだった。
現行「鵜飼」は、前シテ(老人)が中入し後シテ(鬼)となって登場するが、古くは「松山鏡」などと同工で前シテが中入せず舞台に残り、別の役者が後シテを演じたことも考えられる。中入でアイを出さない演出がありその名残かもしれない。今回は、江戸期以前の演出を考察し上演する。
出演者紹介
CAST

林 宗一郎
Hayashi Soichiro
日本能楽会会員

茂山千三郎
Shigeyama Senzaburo
日本能楽会会員

橋本 光史
Hashimoto Koji
日本能楽会会員

観世銕之丞
Kanze Tetsunojo
日本能楽会会員

観世 淳夫
Kanze Atsuo